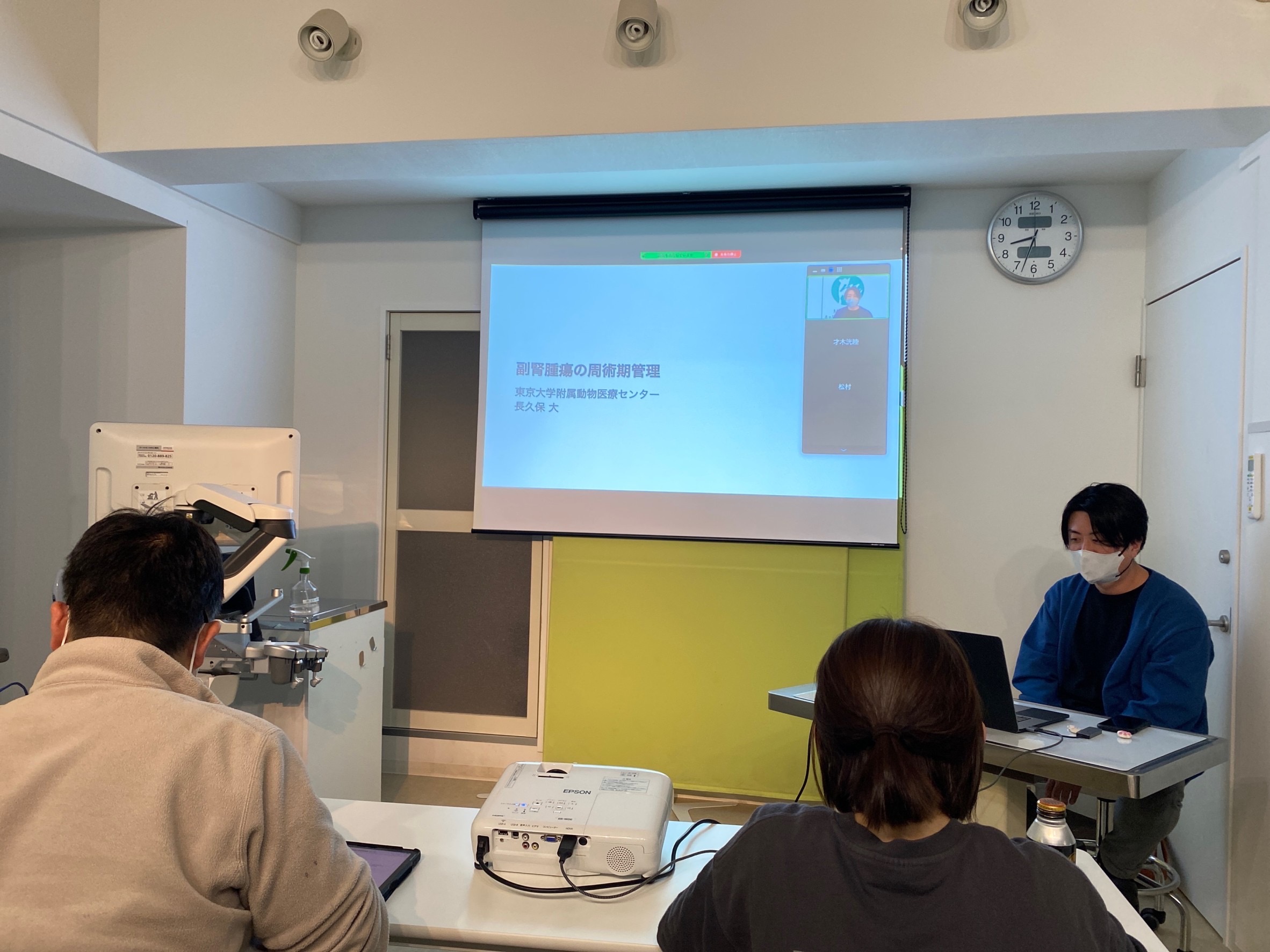お知らせ
NEWS
2023.8.28 皮膚科勉強会
2023年8月30日
今回は犬と猫の皮膚科の村山信雄先生に「犬の感染症 Part2」というテーマで講義していただきました。マラセチア皮膚炎、ニキビダニ症、皮膚糸状菌症の症状や検査法、治療法について教えていただきました。
マラセチア皮膚炎は脂の多い頸部腹側などで発症しやすく、症状は急性期と慢性期に分けられます。皮膚検査においてマラセチアが検出されなくても、症状からマラセチア皮膚炎と診断し治療的な評価を行うことがあります。
ニキビダニ症の初期の症状は脱毛斑や面ぽうですが、悪化すると炎症が広範囲に広がり蜂窩織炎を起こすことがあります。ニキビダニ症の診断では原因となるニキビダニを検出することが重要です。近年ではニキビダニを駆虫できる成分が含まれているノミダニ予防薬もあり、ニキビダニ症自体の発生は少なくなっています。
犬の皮膚糸状菌症では脱毛や鱗屑に加えて丘疹、紅斑が見られます。検査方法はいくつかありますが、いずれも検出率が100%ではありません。より検出しやすい器具を使用したり、採材する部位を見極める必要があります。抗真菌薬の内服により治療します。また、生活環境中の糸状菌を除去することも有効です。
遭遇する機会が少ない皮膚疾患でも見逃すことがないように、様々な可能性を考えて診療にあたりたいと思いました。
獣医師 菅原里佳
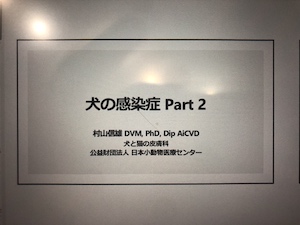
2023.7.27 腫瘍科勉強会
2023年8月5日
今回は当院の腫瘍専門外来の中野優子先生に「腫瘍科しくじりあるある」というテーマで、中野先生ご自身の経験や、紹介のあった症例で感じた、腫瘍疾患の治療中に特に注意するべきことをお話ししていただきました。
継続してみていた疾患以外の新たな腫瘍の発見が遅れてしまったり、手術で腫瘍切除後にリンパ節や他の部位の転移が見つかったりすることがないように、身体検査や画像検査など、ルーティーンの検査を見逃しがないようにしっかりと行なっていきたいと思います。
また、後半では抗がん剤治療中によくある質問についてのお話もしていただきました。副作用や抗がん剤の排泄、サプリメントの使用について改めて聞くことができました。サプリメントは種類によって抗がん剤の治療効果を下げる場合もあるため、注意が必要です。
獣医師 安平芙由
2023.7.13 眼科勉強会
2023年7月14日
今回はぺテモどうぶつ医療センター相模原の寺門邦彦先生に、「外傷性眼疾患」について講義していただきました。
外傷性眼疾患には、外傷性角膜潰瘍・角膜炎、結膜下出血、眼瞼の外傷、瞬膜の外傷、眼球脱出があります。外傷性角膜潰瘍・角膜炎は異所性睫毛や眼瞼内反、異物などが原因で生じ、角膜に当たっているものを取り除くことが治療法となります。SCCEDsと呼ばれる角膜の疾患と所見が似ていますが治療法が異なるため、異物を見逃さないことが重要です。結膜下出血の多くは交通事故や喧嘩が原因となり、診断時にぶどう膜炎や角膜潰瘍を併発していないか、確認する必要があります。咬まれたことによる眼瞼外傷では、強膜に穴が開き眼球が虚脱していないかの確認も必要です。瞬膜に裂傷があり縫合する際には、角膜に縫合糸が当たらない部位のみを縫い合わせます。
眼球脱出は緊急疾患であり、できるかぎり早期に眼球整復を行うことで失明のリスクを下げることができます。損傷が激しく眼球整復が難しい場合には眼球摘出を行います。
日常の診察で角膜潰瘍に遭遇することは多くありますが、難治性の角膜潰瘍の場合に外傷がないかどうか、注意深く観察していきたいです。
獣医師 菅原里佳

愛玩動物看護師向け腫瘍セミナー
2023年7月8日
今回は、当院の腫瘍専門外来担当の中野優子先生に、「犬のリンパ腫」についてのセミナーを行なっていただきました。
リンパ腫とは、リンパ球という血液の免疫細胞が腫瘍化した疾患で、リンパ節や脾臓などのリンパ組織や、消化管や皮膚にもできる腫瘍のことです。
セミナーでは、このリンパ腫の種類、診断方法、診断するための細胞診検査の染色の方法、リンパ腫によって起こる血液や体調の異常、抗がん剤による治療と副作用のことなどをお話していただきました。
リンパ腫にも様々な種類があり、細胞診の検査で診断できるのは中~大型のリンパ球が50%以上増加した高悪性度のリンパ腫のみで、小~中型のリンパ球のリンパ腫は病理組織の検査に出す必要があります。また、それぞれ細胞診のスライドでどのように見えるかも異なります。
治療の話では、使用する抗がん剤には様々な種類がありそれぞれどのような副作用が起こるのかや、副作用で苦しむことが無いように予防的に吐き気止めのくすりを使うなど、改めて詳しく聞くことができとても勉強になりました。
動物看護師として、検査の時には診断に必要な細胞診の標本を正しい方法できれいに染色できるように心がけたいと思いました。
また、実際に治療する子がいる時には、抗がん剤治療をしている子にどんなことが起こる可能性があるのかを把握し、何か異常があったときにすぐに気づけるように、動物たちをよく観察していきたいです。
愛玩動物看護師 瀬尾美帆
2023.7.3 皮膚科勉強会
2023年7月5日
今回は犬と猫の皮膚科の村山信雄先生に「膿皮症」をテーマに講義していただきました。
犬の痒みを生じる皮膚疾患のうち、膿皮症は細菌感染によるもので、飼い主様が「痒がっている・舐めている」「かさぶたがある」「毛が抜けている」といった主訴で来院されることが多いです。膿皮症でみられる皮疹には表皮小環、紅斑、脱毛斑、丘疹が多く、これらは皮膚に常在する細菌が表皮または毛穴に感染し、感染が拡がるために見られる状態です。このような皮疹がみられたら膿皮症を疑い検査、治療を進めていきます。また、今回はよく見る症状以外に、稀に遭遇する粘膜皮膚膿皮症、深在性膿皮症についてもお話いただきました。なかなか普段の診療で見ることはないため、今回のお話を忘れず実際に症例が来た時には適切に対応していけるようにしたいです。
後半は膿皮症の治療について詳しくお話しいただきました。膿皮症の治療管理のためには、ブドウ球菌の管理、健康な皮膚作り、背景疾患の評価が必要です。菌の管理には全身性抗菌薬やシャンプーを使用し、必要に応じて培養検査を行います。シャンプーは膿皮症に大変効果的ですが、「量・順序・頻度」が重要なので適切な方法を飼い主様にお伝えし、実践していただく必要があります。よくある疾患だからこそ、適切な抗菌薬、シャンプー療法を用いることが重要だと感じました。
獣医師 安平芙由

2023年5月25日 愛玩動物看護師向け麻酔セミナー
2023年6月13日
今回は、岐阜大学の柴田先生による看護師向けの麻酔セミナーとして「麻酔器と生体モニタ」をテーマに講義を行っていただきました。今回の講義では、麻酔前と麻酔後の管理や痛みの評価など動物にかかわる事だけでなく麻酔器や麻酔をかけるのに必要な道具、麻酔回路といった細かな器械まで説明していただきました。お話を聞くまでは、麻酔後の管理が大切であると考えていましたが、麻酔後に適切な管理を行うには麻酔をかける前の状態をしっかり把握することが必要であると学びました。麻酔前後の状態を比べることでいつもと違う点や痛みの状態、いま必要な治療や看護は何か理解することに繋がります。手術後は日に日に状態が変化しその子のその日に適した看護を提供する為には動物をよく観察することが私たち看護師に出来ることだと感じました。
また、表情の変化を読み取る難しさを学び、日頃から意識して目や耳、鼻の位置を観察することが必要だと思いました。細かな変化を見逃さないように観察力を身につけて行きたいです。
わんちゃんやねこちゃんの痛みによる負担や不快を減らせるように痛みの管理の手助けができたらいいなと思います。
愛玩動物看護師 樋山実希
2023.4.24 皮膚科院内セミナー
2023年4月25日
今回は犬と猫の皮膚科の村山先生に 「犬の痒みの考え方」をテーマにご講義していただきました。
犬の皮膚病を診断する際には、症状から病態を疾患群で捉えることが重要です。
痒みを生じる疾患群には、感染症、皮膚炎、先天的要因、外傷などがあり、紅斑、丘疹、脱毛などがある場合には感染症、全身症状を伴う脱毛などがある場合などでは内分泌疾患が疑われます。
痒みを伴う疾患では、痒み止めとしてオクラシチニブ(アポキル)を用いる事がよくありますが、本薬物は即効性が期待でき、長期投与の安全性が高いことが知られています。
後半では、そのオクラシチニブの投与量や投与のタイミング、副作用について論文に基づいた解説をしていただきました。
今回は、日頃よく使用する薬物について理解を深める機会となり、今後も薬物の特性や副作用についてしっかり勉強し、理解して使用することが重要であると感じました。
獣医師 才木洸睦
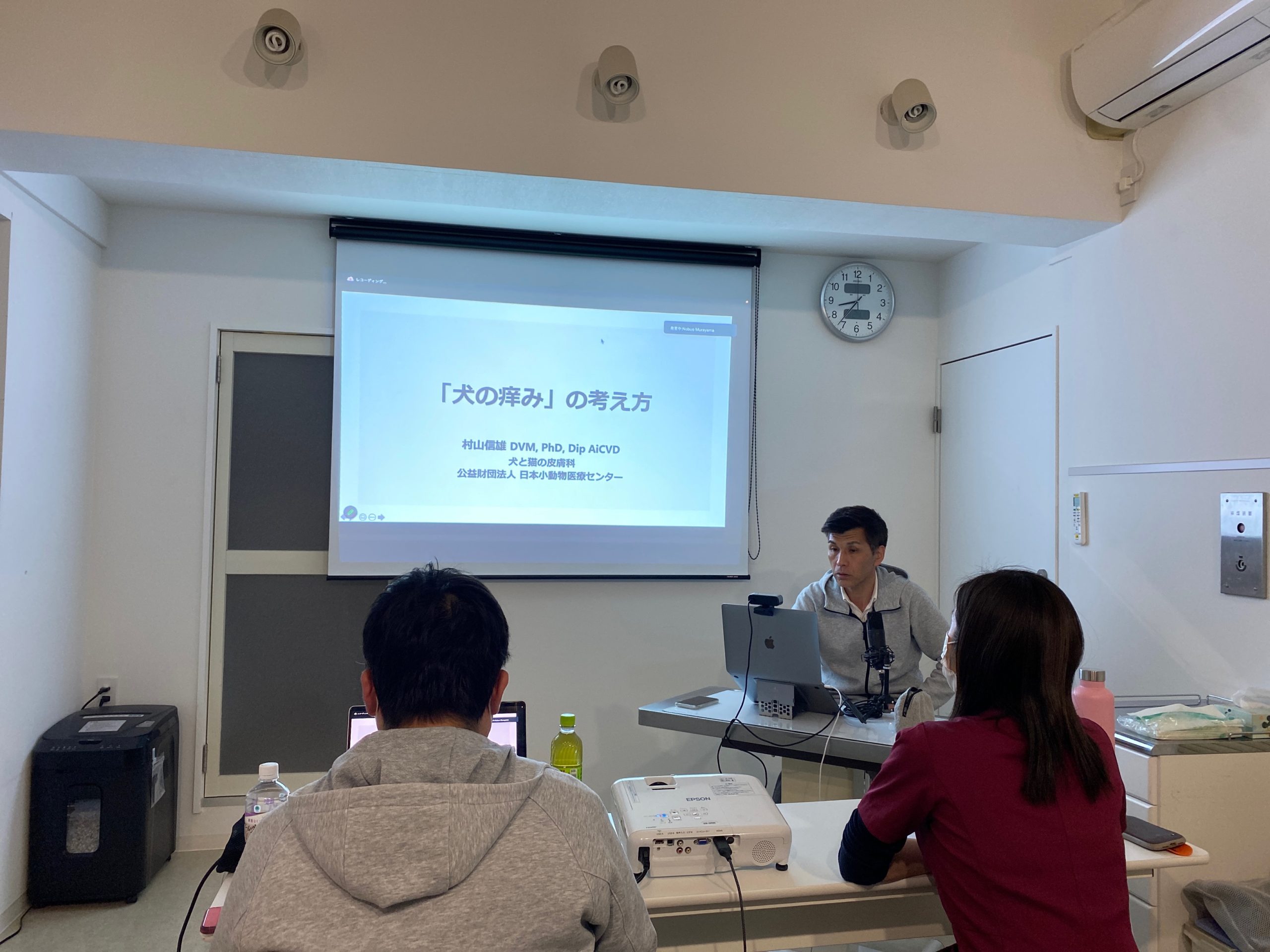
2023.4.6 動物ケアスタッフ向け腫瘍内科院内セミナー
2023年4月16日
今回は動物ケアスタッフ向けで、当院の腫瘍専門外来担当の中野優子先生に「犬と猫の口腔内腫瘍 2023」のテーマで講義をしていただきました。
口腔内腫瘍は細胞診だけでは良性か悪性の判断が難しいため、病理組織生検による確定診断が必要であること、転移の可能性についても詳しく解説していただきました。
特に犬の口腔内腫瘍については、悪性黒色腫がほとんどを占めることや、挙動が悪性と似ている良性腫瘍も存在することについての説明が興味深かったです。また、悪性黒色腫の治療について、局所病変の外科切除後の抗がん剤治療の効果がまだ十分に検証されていないことについても触れられており、最新の情報を学ぶことができました。
講義の中で、腫瘍の大きさが2cm以下で治療ができると長期間の生存が期待できることも知り、早期発見と治療の重要性を再認識しました。
今後もより多くの動物たちの健康を守るために知識を活かしていきたいと思いました。
動物ケアスタッフ 高須喜大
2023.3.30 腫瘍内科院内セミナー
2023年4月1日
今回は当院の腫瘍専門外来担当の中野優子先生に「犬の移行上皮癌2023」をテーマに講義していただきました。膀胱腫瘤の診断には外力カテーテル法を用いた生検による細胞診と病理診断の組み合わせが有効です。エコーで膀胱を確認しながら、カテーテルで目的の腫瘤の一部を採取し、診断します。適応条件はありますが、有効診断率は高いとされています。加えて、遺伝子変異の有無を調べる検査を行うこともあります。
後半では新たな分子標的薬について、論文をもとに詳しくお話ししていただきました。従来の薬と比較して高い治療効果が認められており、治療の選択肢が増えることが期待されます。
移行上皮癌の臨床症状は尿路感染症のものと似ています。エコー検査時に膀胱・尿道の異常を見逃さないことが重要だと感じました。
獣医師 菅原里佳
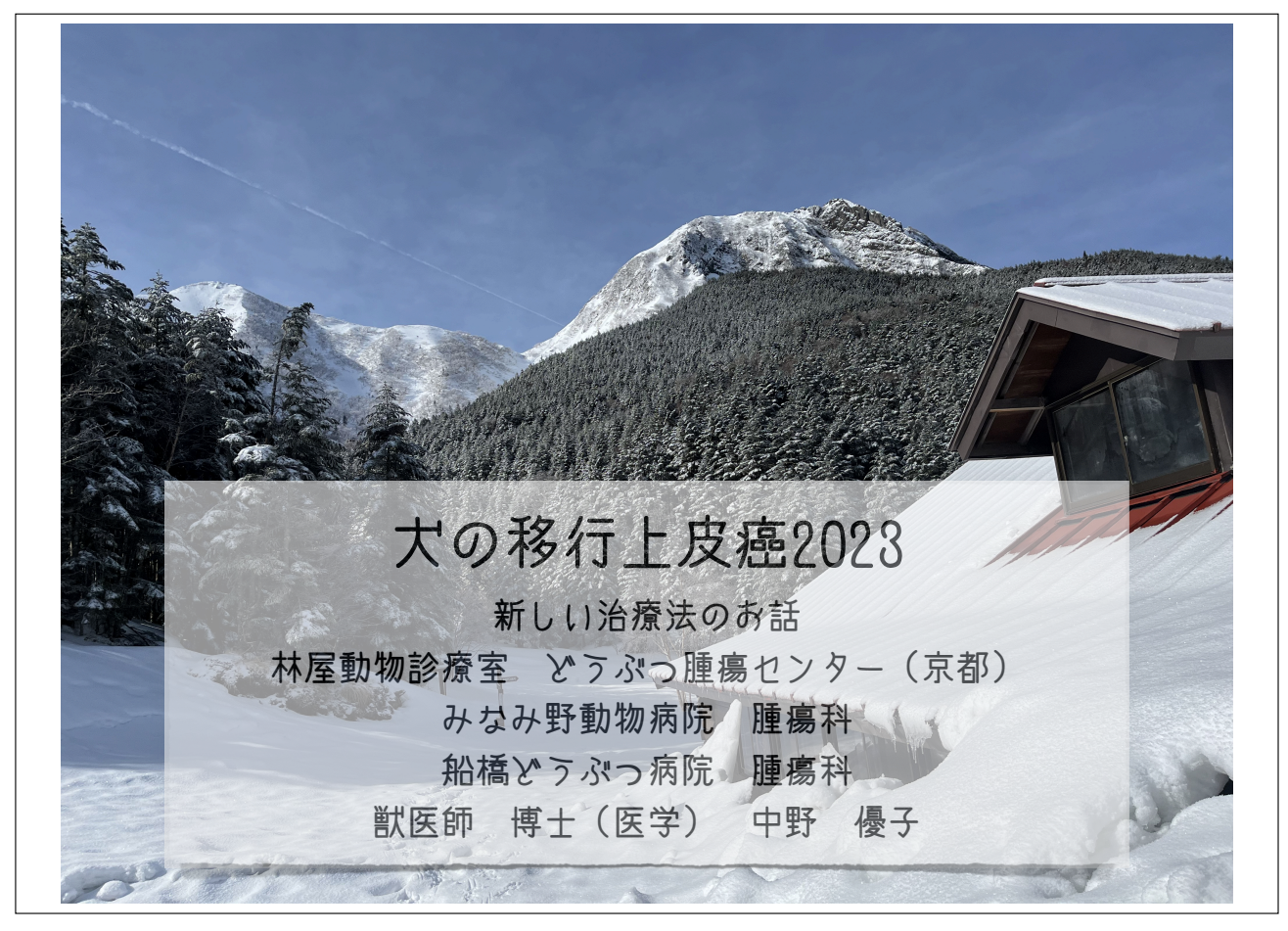
2023.3.20 麻酔科勉強会
2023年3月25日
本日は東京大学の長久保先生に「副腎腫瘍の周術期管理」「循環の生理学」をテーマに講義していただきました。
機能性の副腎腫瘍は、周術期に特に注意する点がいくつかあリ、副腎皮質機能亢進症では術後の血栓症のリスク、褐色細胞腫では血圧上昇などが考えられます。また、アドレスタンによる治療を行なっている場合は、内因性のコルチゾール不足を予防するため手術前日と術後数日の休薬が必要になります。術前からしっかりと疾患のコントロールをすること、起こりうる事態を想定して適切に対応していくことが大事だと感じました。
後半は「循環の生理学」についてお話いただき、周術期に血圧を維持する目的や、血圧・心拍出量が循環にどのように作用するかを理論的に教えていただきました。難しい部分もありましたが、改めて基礎の重要さを感じたので今後もきちんと勉強していきたいです。
獣医師 安平芙由